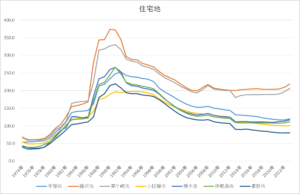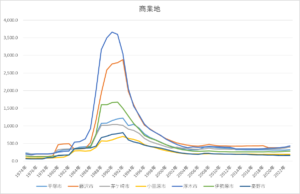湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備に関し、2024年4月23日に公募設置等計画の認定があったと発表されました。
公募設置等計画の有効期限は、2024年6月28日から2044年6月27日です。
一緒に、計画概要が発表されています。
(https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/common/200158064.pdf)
この中に記されたスケジュールによると、2024年4月から契約手続き説明会があり、7月から施工となっています。
そして、2025年11月にグランドオープンといった計画です。
地域住民向けの説明会が開催され、市長が登場したといった話は耳にしました。
2024年6月の平塚市議会でも複数の議員よりこの事業に関して質問が出たようですが、これらの内容が明らかになるのはもう少し先になりそうです。
いずれにせよ、工事は始まるでしょう。
2013年12月に「湘南海岸公園再整備計画」が策定されて10年以上になりますが、素晴らしい跡地活用が実現することを期待したいと考えます。
■関係URL